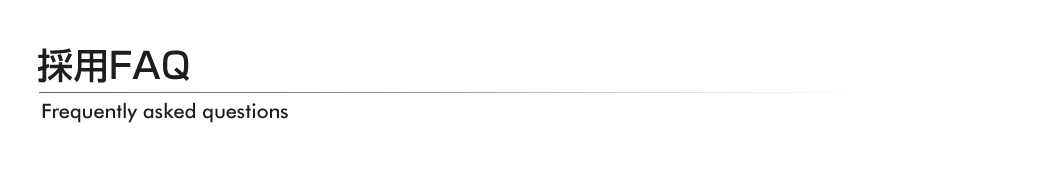
面接や説明会で寄せられた採用にまつわる、よくある質問をまとめています。企業選びの参考にしてください。(データは2015年のものです)
- 仕事内容を教えて下さい
-
客先常駐はなし。受注案件は全て自社内で対応します。
システム開発業界では、下請け、あるいは孫請けとして他の会社に派遣されて開発メンバーに入り、開発の一部分のお手伝いを行う、いわゆる客先常駐(技術者派遣、SES)という形での開発形態が9割を占めていると言われていますが、当社ではこのスタイルの開発を行っていません。
基本的に当社では、取引先企業から直接「こんなことがしたい」という相談を受けて、お客様が抱いている悩みや抽象的な要望を専門家としての視点で助言・具体化し、お客様が満足できるような最適な形のシステムとして最後まで責任をもって創り上げるという、システム開発における全工程を担当しています。
一般的な開発会社でよくあるような元請け会社からの理不尽な要求が来ることもなく、比較的スムーズな状態でプロジェクトの最初から最後までに携われます。
- 仕事の工程(フェーズ)を教えて下さい
-
システム開発の全工程を自社内で対応しています。
プロシェクトにもよりますが、当社では概ね以下の様な形で工程を分けています。
- 1. 要件定義フェーズ
- 2. 外部設計(基本設計)フェーズ
- 3. 内部設計(詳細設計)・開発(製造)フェーズ
- 4. 試験フェーズ
- 5. 保守運用
番号が若いフェーズ(上流工程)ほど、知識と経験が求められますが、社内で着実に実績を重ねていけば、徐々に上流工程で活躍できるチャンスがあります。
- 開発環境を教えて下さい
-
原則的に最新のPCとマルチモニタ、そしてハイバックチェアを支給します。
当社では、開発者には最大のパフォーマンスを発揮してもらいたいという観点から、各担当者のデスクには原則的に最新のデスクトップPCと液晶モニタを2台以上を支給し、さらに腰痛になりにくいハイバックチェアを各デスクに配することにしています。また、ファイルサーバや情報共有システムを含めた各種社内情報システムも自由度とリアルタイム性が高いものを多く採用していますので、ストレスのない開発が可能となっています。
ただし、支給するPCのスペックは一定の性能(~Core i5程度)までに制限しています。
これは、長時間のコンパイルが必要になるような言語での開発が少なくなっていることと、お客様側の環境よりも開発者の環境が優れていた場合にコードの最適化や高速化を怠ってしまう可能性があるためです。(大規模システムに必要になるGPGPUやオンプレミス/クラウドのハイスペック環境については必要であれば別途使用可能です)実際の開発では仮想化ソフトウェアとGit等のバージョン管理ソフト、Redmine/Wiki等のOSS等を用いて行うことが多いですが、実際のコーディング作業環境については個人の裁量に任せられます。好きなIDEやエディタなど、自身が最も高いパフォーマンスを発揮できる環境で開発してください。
なお、言語やDBについては特に決まりありません。お客様が求めるシステムについて、最も適した言語やOS等に合わせて開発を行います。 - 取引先はどのような会社ですか?
-
皆さんも名前を知ってるあの会社など。
皆さんが名前を知っている会社、あるいはきっと名前を聞いたことがある施設や商品に携わっている会社、特定分野で世界的に評価が高い会社などばかりです。
積極的に営業を進めているわけではないので取引先は多いとは言えませんが、基本的に顧客との直取引がメインなので、求められる責任は大きくなるものの、仕事で得られるやりがいも大きいと思います。
- 技術者はどのような層がいますか?
-
プログラマ、システムエンジニア、プロジェクトリーダー。
明確な垣根はないのですが、大きく分けるとプログラマ(PG)、システムエンジニア(SE)、プロジェクトリーダー(PM)の3種類が存在します。
他のシステム開発会社では、古臭い設計のシステムをシステムエンジニアから押し付けられて、設計書通りにプログラムを翻訳する「コーダー」や、プログラムが当初の設計通り動作するかどうかを毎日ひたすらテストする「テスター」と呼ばれるポジションが存在しますが、当社にはこれらの「コーダー」や「テスター」といった職種は存在しません。
あくまで「技術者として独り立ちできる」人材になってもらうことを目指しています。
- プログラマはどんな仕事をするのですか?
-
システムを実際に作り上げる「大工・職人」。
お客様が求める要求をもとにシステムエンジニアが大枠を設計した概要から、実際にシステムとして動かすために、状況に応じて最適なプログラム言語を用いての開発を担当します。
家を建てるフェーズになぞらえれば、設計書を見ながら実際に建築を行う大工・職人さんに当たります。
当社のプログラマは、自分が最適だと思う新しいシステムを自分で考えて練り上げていくという、プログラミングが本来持つ「楽しい」作業を仕事にすることを重視しています。自分の担当分はテストも行いますが、客観性を担保するために他の担当者がテストすることもあります。
このポジションでどれだけの「技術的な引き出しや発想力」を多く持てるかで、将来が大きく変わります。
- システムエンジニアはどんな仕事をするのですか?
-
お客様の要望を設計書に落としこむ「設計士」。
お客様からヒヤリングを行い、各種調整の上で、お客様にとって最適な要求をシステム化するためのおおまかな方針の設計書を作成したり、動作環境の選定、プログラマに対して実際に開発を行う上での指針を示します。
家を建てるフェーズになぞらえれば、設計書を作成する建築設計士に当たります。
当社では多くの「技術的な引き出し」を持っていなければ、数ある選択肢の中からお客様に最も良いものを提案できないと考えているため、原則的に社内外を問わず一定期間のプログラマ経験を積んだ方でなければ、システムエンジニアになれない形となっています。
大手開発会社ではコミュニケーション重視の採用を行った結果、文系出身者に半年程度の研修を行って十分な経験を積まないままにシステムエンジニア職に配属される事が多いですが、その結果、持っている知識や引き出しが少ないままにシステム開発を進めてしまうことになるため、結果的に出来上がるものの品質が好ましくなかったり、理想と現実が乖離する等、いわゆるデスマーチや赤字化などのトラブルになる事が多くなるという問題を抱えています。
しかし、当社では上述のような全く異なるアプローチで採用・業務を行っているため、基本的にそのような状況になることはありません。
- プロジェクトマネージャはどんな仕事をするのですか?
-
スケジュール、人員管理など、プロジェクトを成功に導く「責任者」。
お客様とシステムエンジニアやプログラマを含めた全員の調整を行い、担当プロジェクトを確実に成功させるために進捗状況を定期的に確認したり、スケジュールや予算、関連メンバーの調整など、全体を俯瞰して調整・対応する役目となります。
家を建てるフェーズになぞらえれば、建築全体の管理・監督を行う責任者に当たります。
プロジェクトの管理進行には幅広い知識と経験が求められるため、原則的にシステムエンジニアとしてある程度経験を積んでからプロジェクトマネージャになることが多いです。
- 作業場所は客先に常駐する形になるのですか?
-
いいえ、客先常駐や出向はありません。
当社では良い物を作るためには社員間のコミュニケーションや協力が不可欠であり、技術者は最善の開発体制で開発を行うべきだと考えていますので、全て自社内にて仕事を行うという形になります。そのため、本人が強く希望する場合を除いては出向などはありません。
ただし、当然ながら打ち合わせや納品直後のサポートのため等で出張や現地作業が発生することはあります。
- 仕事では上流工程に携われるのでしょうか?
-
はい。知識と経験が備われば上流工程を担当できます。
ソフトウェア業界は建築業界などと同じく、多重請負構造になりがちという性格を持っており、殆どの会社はこれに取り込まれていますが、当社ではできるだけ同業他社からの下請けは行わない、という思想で仕事をしています。
つまり、他社からの指示によって製造(プログラミング)だけを担当したりするわけではなく、直接お客様と顔を合わせて、お客様が求めるものをヒヤリングし、最適なシステムを設計し、社内で製造する、という一連のシステム開発フローを当社で担当します。
そのため、最初は知識を得たり経験を積むために下流工程(製造・テスト)がメインになる可能性は高いものの、能力と経験によって徐々に上流工程(要件定義・設計)に携わることが出来るようになっています。
- 会社に寮はありますか?
-
住宅手当制度と社宅制度あり。
寮はありませんが、住宅手当制度と社宅制度があります。
住宅手当は、個人で借りた部屋が勤務地から一定距離内であれば月3万円までを支給するものです。
社宅は、敷金や引越し費用などの全額と、家賃の半額程度を会社で負担するものです。社宅制度については、会社都合で転勤が発生した場合などに適用されます。(社宅制度は原則的に入社時の配属先決定時には適用されないので注意してください)
- 配属先や、やりたい仕事を自分で決められますか?
-
配属、仕事は本人の希望も踏まえて長期的な成長を見越して決定します。
個人の能力や希望を考えて、原則的に最も適していると思われる部署に配置し、仕事に携わってもらいます。
ただし、将来の成長を考えると色々な分野に携わって、様々な知識と経験を得るべきですので、長い目で見ると得意でない仕事を担当してもらうこともありえます。